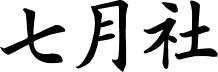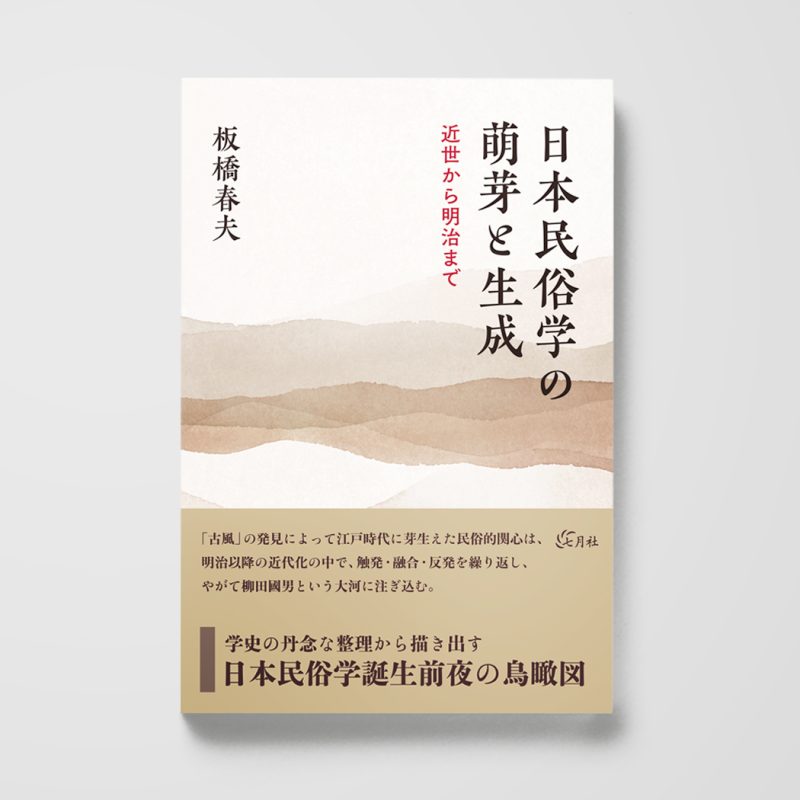素朴に考えよう
中村三春(『物語主義』著者)
本書『物語主義 太宰治・森敦・村上春樹』の巻末に、筆者の主要著作年譜を付してある。その中に、『物語の論理学 近代文芸論集』(2014年2月、翰林書房)のタイトルが見える。同書と本書は、物語を主要なコンセプトとした点において共通し、その起点としてロラン・バルトの「物語の構造分析序説」や野家啓一の『物語の哲学』を置いたことまで同じである。その意味で本書は同書の一種の続編としての位置を占めることになるのだが、一つ大きな違いがある。
同書では、中上健次の『風景の向こうへ』などで示された「物語」と「文学」、あるいは伝統的な「物語」と近代的な「小説」とを対比する理論を批判的に継承している。中上は、伝統的な「物語」が共同体の〈法=制度〉の定型的な表現であり、「文学」が自我の告白中心のやはり制度的な所産であったのに対して、「小説」を様々な「交通」によって両者の定型性・制度性を打ち破るようなジャンルとして定義した。しかし同書において筆者は、物語の一貫性の観点から見れば、伝統と近代との間の切断線は明瞭ではなく、むしろそれらはいずれも物語における〈変異〉(mutation / variation)の多様なあり方にほかならないのではないかと認め、その観点から、明治より現代に至る物語のテクストを論じたのである。
一方、このような、いわば歴史的な荷重を負った物語観に対して、本書における物語のとらえ方は、至ってシンプルなものである。それはすなわち、〈物語は自らを見せつけ、読ませようとする〉こと、あるいは、バルトの言葉を借りれば、物語は〈物語の誇示〉そのものを基本的な目標とする、ということである。〈物語は本質に先立つ〉とは、そのことを意味している。
もっとも、『物語の論理学』においても、〈物語の誇示〉の方略として、物語における〈誘惑〉と〈差異化〉を筆頭に挙げているから、やはり両者は連続するものなのだが、とにかく本書が基底においたのは、《素朴に考えよう》ということに尽きる。その理由は、近来、物語論が盛んに行われる反面、むしろ論理構成が大げさになり過ぎることにより、本来の物語のあり方が見失われる危惧があると考えたからである。
この見方に応じて、本書における物語の定義もまた、何にせよ物が語られればそれは物語であり、語ること、および語られたものはすべて物語(narrative)であるとする最小の(ミニマルな)記述としている。たとえば、野家が歴史や科学も文芸とともに物語に包括してとらえたことを思えば、小説・戯曲だけでなく詩もまた物語なのである。それらはすべて、それ自体の〈誇示〉をすることを目標として、あるいはそれを前提として、その内容や構造が設(しつら)えられているのである。その発生でも、それによる帰結でもなく、そこにある物語、あるいは、物語がそこにあることそのものを凝視すること。従って本書の発想法は、現象学・記号学・解釈学のそれに近いだろう。
二部構成の本書において、「Ⅰ 物語と虚構の文芸学」に収めた4章は、それぞれ虚構と物語の関係、作者の理論、コンテクストの理論、そしてテクストと論述における例外性の理論を扱っており、いずれも文芸理論では古くて新しい問題を論じたものである。これは筆者の初期の単著である『フィクションの機構』(1994年5月、ひつじ書房)の理論の、取りあえずの完結編と考えている。続く「Ⅱ 小説と映画の物語」の全10章は、『白樺』派、芥川龍之介、太宰、森、村上、そして小川洋子の作品と、またそれを原作とした映画について検討したものである。それぞれの論述の過程において、小説の定型や再帰性、語りや文体、翻案や映画化などの第二次テクスト性、物語の公理やフィクション性との関わり、そして何よりも、物語主義の観点から、それらが自らをどのように〈誇示〉しようとしているかに重点を置いて論じたのである。
これらのテクスト分析には様々なテクスト理論が援用されているが、根底にあるのは、ネルソン・グッドマンの『芸術の言語』や『哲学とその他の芸術・学問における新たな構想』(邦題『記号主義 哲学の新たな構想』)などによって拓かれた分析美学の手法である。これは、思考上の夾雑物を一切排して、物語がそこにあることに注目するための理論として、最適な解を与えてくれる。『世界制作の方法』も併せて、これまで筆者の物語やテクストに関する考え方を支えてくれたのがグッドマンの思想であった。これは『フィクションの機構』以来、変わっていない。本書では具体的には、リアリズム概念については『芸術の言語』に、作品の存在様態や第二次テクスト性については『新たな構想』に負っている。
さて、『物語の論理学』と本書、さらにそれ以外のこれまでの著書において、小説テクストと物語の繋がりについては継続的に論じてきた。ただし、上に書いたような、〈詩もまた物語である〉という主張は、大方にとってはかなり奇異に響くものだろう。本書をまとめた後の次の課題としては、この、物語と詩との結びつきについて、理論的かつ歴史的に検証することである。これはまた、前著である『ひらがなの天使 谷川俊太郎の現代詩』(2023年2月、七月社)で論じた内容の延長線上に現れた課題でもある。詩もまた物語なのだ。筆者はこの後、この問題に注力しようと考えている。