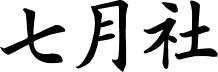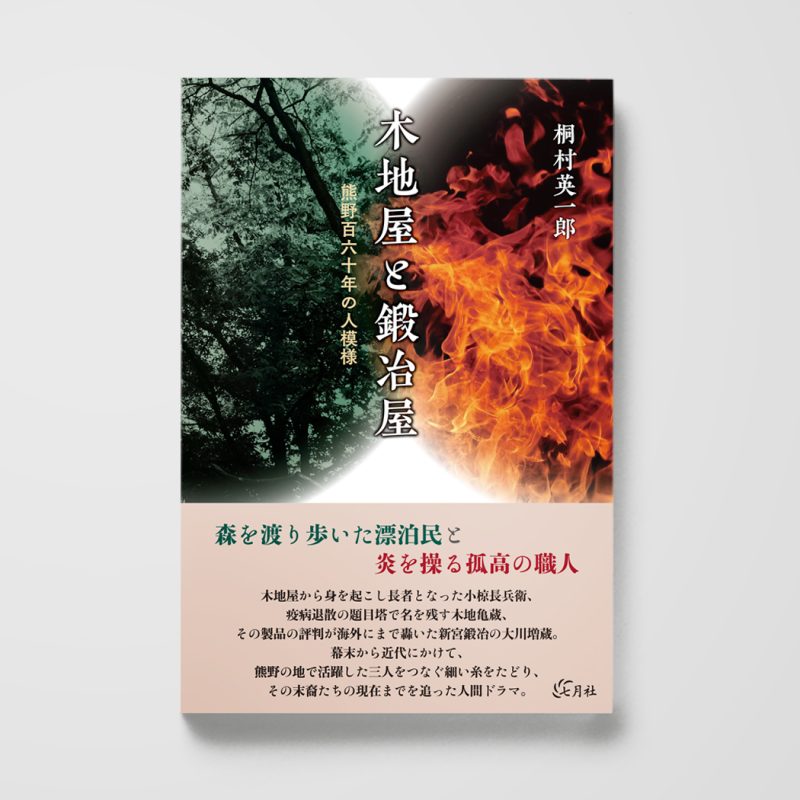民俗学のまなざしと麦の座標/野本寛一
民俗学のまなざしと麦の座標
野本寛一(『麦の記憶』著者)
ビール麦や、健康食品・地域興こしの素材とされるモチ麦、農協がかかわる一部の小麦栽培などを除いて、この国の風景の中から主食としての麦栽培にかかわる種々の営みや耕地に育つ麦の姿が消えて長い時が流れた。麦踏みも、麦秋の景観も、麦コナシにいそしむ人びとの姿も総じて過去のものとなってしまった。それは、日本人が米に次ぐ穀物として主食の一角に加え、その増産に努めてきた麦である大麦を素材とした麦飯が食卓から消えてしまったからである。また、小麦系の食べものは現今でも多食されてはいるものの、その原料の小麦は90%を輸入に頼っているからだ。食糧構造の中における大麦系の麦の比重は昭和三十年前後から始まった高度経済成長の歩みとともに軽くなり、昭和四十八年の石油危機のころにはもう麦飯が食卓にのぼることはなかった。
「麦の記憶」をふり返り、反芻すべきだと考えた理由はいくつかある。飽食の時代と言われ、グルメブームの煽動に乗り始めてからも久しい。一方厖大な量の廃棄食品・食品ロスが批判の対象になってからも根本的な改善はなされていない。過剰に用意された節分の恵方巻の残余はどこへ行くのか。クリスマスケーキにしても同様である。コロナ禍における需給不全は別途として、これまでの廃棄食物の多さは世界の心ある人びとから顰蹙を買ってきた。しかも、こうした状態が、カロリーベースでの食料自給率三七%という極めて危い中で行われているのである。厖大な債務にまみれる中での身の丈に合わぬ浪費、華美なるものへの単純な願望も省察されなければならない。
高度経済成長期以前、この国の子供たちは皆、一粒の米、一粒の麦を粗末にすることを強く戒められて育ってきた。昭和初期までは、稲の籾摺り作業を自家で行うのが一般的だった。籾摺り作業をすると、納屋の土間などに米や、割れた米、未熟の米がこぼれる。このような米を丁寧に拾い集めて竪臼・横杵でハタいて(叩いて=搗いて)粉化し、その粉を捏ねてから蒸し、「ネコ」と呼ばれるカマボコ型の棒の形に整え、これを切って食べる方法があった。叩くところから静岡県ではこの餅を「オハタキ」と呼んだ。オハタキにする米は粳米・屑米が多かったのでオハタキは灰色をしていたし、糯種ではないので粘着力がなかった。静岡県藤枝市蔵田の藤田賢一さん(明治三十五年生まれ)は籾摺りの日の拾い米で作ったハタキモチのことを「ツボモチ」と称して臼や神棚に供えて、家族も食べたと語る。ツボモチとは「粒餅」の意だと考えられるが「土穂餅」と見る地方もある。藤田さんは、「師走川渡らぬ先にツボモチを」という口誦句を伝えていた。「籾摺りは十一月中に終えよ」ということである。また、「ツボモチをよそ(他家)へやるとツボモチが泣く」とも伝えていた。「ハレの餅」ではない、「始末」「倹約」の餅、食素材を大切にする褻の餅なので、家族で内々に大切に食べるものだとする心意が見られる。米粒・麦粒などの穀類を一粒たりとも無駄にしてはいけないという伝統が儀礼として定着していたのである。
飽食の中に生きる現代人は手のとどく過去の人びとの食べものに対する心がまえを忘れてはならないのである。本書の中で詳述する通り、麦という穀物は、刈り取り以後、麦コナシをして、精白する。飯にするのにも手がかかる。その間の手間隙には想像を絶するものがある。多くの穀物の中で口に入るまでにかけなければならない労力の多さは、何と言っても大麦(皮麦)が一番である。多くの手間と時間をかけてやっと食べることができるのだ。そうした苦労に支えられて命をつないできた麦のことを忘れ去るわけにはゆかないのである。もとより今、こぞって麦飯を食べよ、などというわけではない。麦とともにあった心を失ってはならないのだ。
平素は麦飯か糅飯で、米の飯は盆正月か人生儀礼の折にしか口に入らない時代が長かった。静岡県の大井川中・上流域は知られた茶産地で、お茶の季節には下流部の水田地帯から季節労務者として多くの茶摘み女や茶師と呼ばれる焙炉師が山のムラムラに入った。茶摘み女には麦飯でも、技能者である茶師には米の飯と夕飯酒と呼ばれる酒が付けられるのが一般的だった。静岡県焼津市藤守の加藤正さん(明治三十二年生まれ)は焙炉師として大井川中流域の山のムラムラで茶を揉んでまわった人である。加藤さんは次のような茶摘み唄を記憶していた。
茶揉みゃ米の飯正月か盆か 主もやりたや川根路へ
お茶師ゃ米の飯正月か盆か 親の年忌か嫁入りか
「銀舎利」とも俗称される純白の米の飯が庶民にとっていかに特別なものであったかがわかる。
田植、春蚕あげ、麦刈りが一時に降りかかる農繁期の重い仕事をみごとに為しとげて来た人びと、夜、大麦をエマしておき、朝それを米と混ぜて炊き直し、大家族の飯を用意し続けた人びと、麦コナシで芒の刺激と埃と汗が混じって押し寄せる痒さに耐えた人びとなどの多くは、幽明境を異にしてしまった。たとえ十分なものでなくとも、断片のごときものであったとしても、今記しておかなければ、麦にかかわる多様な苦渋と、その中でも味わったであろう充実感などは永久に忘れ去られてしまうのである。私には僅かな麦の記憶があるだけなのだが、それをもとにして各地の方々から麦にかかわる多くの体験と伝承を聞いてきた。それは、体系的、計画的なものではなかったのだが今となっては貴重である。書きとどめるべきだという思いが強く湧いた。
近代以降もこの国の人びとは己が命を支える主食食物としての麦に大きく依存してきた。その麦に対して日本民俗学のまなざしは決して細やかで、温かく、行きとどいたものだとは言えなかった。それでも、これまで、麦の様々な側面、麦にかかわる様々な営みの一定の部分に光を当て、優れた成果を示しているものも多々ある。それらの多くについては本書の各章で引用または例示させていただいている。多くの成果の中でも、埼玉県内の事例を扱った大舘勝治氏の「麦作」は緻密・精細であり、総合的でもあって学ぶところが多かった。
こうした成果に学びながらも、「麦」と「麦に関する多くの営み」を民俗学の視座から全国的に眺め、総合的にまとめたものは見られないように思われた。なぜこのような状態に至ったのであろうか。その要因の一つは、日本人の食の中核に位置したのが米であり、それを生み出す営みが水田稲作だったからである。そして、米の日常的な食法は「飯」という形態であり、「麦飯」という言葉が纏っている通り、米に麦を混ぜた飯は、晴れの日に食される「白米の飯」に対して、「褻の飯」「粗末な飯」として位置づけられてきたのだった。その上、晴れの日には糯種の米によって餅が搗かれ、これが年中行事や人生儀礼の祝いの食物となり、神饌ともなり、儀礼食ともなってきた。麦の中の小麦は粉化の後様々に加工されて儀礼食にもなったのだが、それらといえども米の餅と対等とは言い難い部分があった。「麦飯」に象徴されるように、麦は常に米の陰に位置し、従属する位置にあり、麦は米を補足するものと見為されてきた。稲(米)は夏作で、麦は冬作であるのだが、人びとは、長く、稲を表作、麦を裏作と称してきた。こうした風潮のもとにあればこそ、麦と日本人の関係を総合的に探究し、まとめてみようという動きが鈍かったのである。
また、民俗学およびその周辺に、起源論・伝播論、特定の栽培物を象徴的指標とする文化論的なものを提示する流れが風靡した時代があった。当然、そうした探究の意義は深いものではあるが、それらは、一国民俗学には荷が重すぎる部分もあり、方法論としてなじまないところもあった。学際的共同研究や国際的共同研究において初めてそれらは可能となる。日本民俗学はまず、この国の民俗を具さに見つめ、社会環境、自然環境や時代変容の中で、その特色を確かめ、生活者とのかかわりを学ぶところから始めなければならないのである。
例えば里芋をとりあげるとすれば、早生、中生、晩生、さらには茎のみを食べる芋など、一体里芋にはどのような種類があるのかを知らなければならない。褻の生活の中でどのように季節適応をし、どの時期にどの種類の芋を主食的に、どのように調理して食べてきたのかを知らなければならない。晴れの食とされた「芋餅」に使われた里芋はいかなる種類で、芋餅に混合物はあったのかなかったのか、晴れの食として芋餅を食べる日、芋をそのままで食べる日は何の日だったのか、里芋の種類と栽培環境──定畑か、焼畑か、水田か、そして里芋の貯蔵法はいかなるものだったのか、里芋以外の主食系食物には何があったのか、──こうした、暮らしに密着した実態から離れた文化論はどうしても観念的になり、暮らしの襞とも言うべき庶民の苦渋や細かい実態を捨象してしまうのである。起源論・伝播論も同じくである。
麦が総合的にとりあげられてこなかったのは、それが常に脇役だったことにより文化論のごとき晴れやかな舞台に登りにくかったということも考えてみなければならない。この国で第一次産業系の仕事に携わってきた人びとは、一人で多くの生業要素にかかわることが多く、身近な自然の中から様々な食素材を獲得し、耕地からもじつに多種に及ぶ食素材を得ていたのである。単一職業的ではなく、「生業複合的」だったのだ。麦栽培もまたその中の一つであった。
かつて属目の風景の中にあった麦は視界から消えた。今、まだこの国の中にはイロリやオクドさんから電子レンジまでを体験し、山中で暮らし塩蔵魚さえ稀とした者で、かつては思いも及ばなかった冷凍食品を容易に口にできるようになった者もいる。生活様式が激変し、それが価値観まで変える現今である。社会生活が激変する時代には、民俗学もその草創期の方法のみに頼っているだけでは道は拓けない。多様な模索があってよいはずだ。社会生活の激変、それに応じて暮らしの細部まで変容・変質してゆく現今なればこそ、個々の民俗や人びとの暮らしぶり、その周囲の景観や栽培作物の消長や変転を克明に記しておく必要が生じてくる。それは民俗学の主要な責務の一つであるはずだ。民俗学は微細な変容に敏感でなければならない。私は、この社会変容にともなう民俗の消滅や変化にも目を注いできたつもりではあるが、個人の力には限界がある。
麦の民俗を総合的に見つめる仕事が稀少である理由の一つには、民俗を学ぶ者の主題や関心が細分化されてきたこともかかわっている。食物としての麦とその食法、栽培作物としての麦の栽培技術、麦にかかわる農耕具・穂落とし具・脱粒具(民具)、麦作にかかわる儀礼、麦栽培や麦コナシにかかわる労働慣行、麦の労働にかかわる民謡、などの側面がある。さらに、地域定点的モノグラフなどもある。分野限定、地域限定で対象物に当たれば精度はあがるが、部分を掘っただけでは麦と人との多様なかかわりが見えてこない。対して、例えば鳥瞰的、総合的に「麦」を描こうとすれば、どうしても粗さがつきまとう。麦の民俗を描き出そうとすれば、農学の成果や歴史学、文化人類学も学ばなければならなくなる。容易なことではない。
気圧され、躊躇し、手を拱いている間に数多の細かい麦の記憶が消えてしまう。麦とともに生きた人びとが幽明境を異にしてしまう──。ある種の危機感を抱き、手のとどく過去の麦に対して遅蒔きながら探索の一歩を踏み出した。本書の骨格はほぼ目次の章立てのごときものであるが、時には麦そのものからはやや距離のあるものもとりあげている。
※本文章は、『麦の記憶』の「序章」より一部を抜粋したものです。
麦の記憶──民俗学のまなざしから
麦の記憶
民俗学のまなざしから
定価:本体3,000円+税
麦と日本人
多様な農耕環境の中で「裏作」に組み込まれ、米を主役とする日本人の食生活を陰ながら支えてきた麦。
現在では失われた多岐に及ぶ栽培・加工方法、豊かな食法、麦の民俗を、著者長年のフィールドワークによって蘇らせる。
目次
序章 麦に寄せて
Ⅰ 麦の栽培環境
一 海岸砂地畑
二 斜面畑と段々畑
三 畑地二毛作と地力保全
四 焼畑と麦
五 牧畑と麦
六 水田二毛作の苦渋─田代・麦代の循環─
七 水田の湿潤度と裏作作物
八 麦と雪
九 沖縄の麦作
十 麦作技術伝承拾遺
Ⅱ 麦コナシから精白まで
一 麦焼きから精白まで─奈良県天川村栃尾の実践から─
二 穂落としの技術
三 脱粒
四 麦の精白
Ⅲ 麦の食法
一 大麦・裸麦の食法
二 小麦の食法
Ⅳ 麦の豊穣予祝と実入りの祈願
終章 麦・拾穂抄
あとがき
著者
野本寛一(のもと・かんいち)
1937年 静岡県に生まれる
1959年 國學院大學文学部卒業
1988年 文学博士(筑波大学)
2015年 文化功労者
2017年 瑞宝重光章
専攻──日本民俗学
現在──近畿大学名誉教授
著書──
『焼畑民俗文化論』『稲作民俗文化論』『四万十川民俗誌──人と自然と』(以上、雄山閣)、『生態民俗学序説』『海岸環境民俗論』『軒端の民俗学』『庶民列伝──民俗の心をもとめて』(以上、白水社)、『熊野山海民俗考』(人文書院)、『山地母源論1・日向山峡のムラから』『山地母源論2・マスの溯上を追って』『「個人誌」と民俗学』『牛馬民俗誌』『民俗誌・海山の間』(以上、「野本寛一著作集Ⅰ~Ⅴ」、岩田書院)、『栃と餅──食の民俗構造を探る』『地霊の復権──自然と結ぶ民俗をさぐる』(以上、岩波書店)、『自然と共に生きる作法──水窪からの発信』(静岡新聞社)、『生きもの民俗誌』『採集民俗論』(以上、昭和堂)、『自然災害と民俗』(森話社)、『季節の民俗誌』(玉川大学出版部)、『近代の記憶──民俗の変容と消滅』『井上靖の原郷──伏流する民俗世界』(以上、七月社)、『自然暦と環境口誦の世界』(大河書房)、『民俗誌・女の一生──母性の力』(文春新書)、『神と自然の景観論──信仰環境を読む』『生態と民俗──人と動植物の相渉譜』『言霊の民俗誌』(以上、講談社学術文庫)ほか
書評・紹介
- 2022-07-30「日経新聞」
評者:神崎宣武(民俗学者) - 2022-09-25「読売新聞」
評者:梅内美華子(歌人) - 2022-10-15「図書新聞」
評者:川島秀一(日本民俗学会会長) - 2023-winter「季刊 農業と経済」
評者:落合雪野(龍谷大学農学部)
ほんのうらがわ(編者による刊行エッセイ)
〈接続する文芸学〉のこと/中村三春
〈接続する文芸学〉のこと
中村三春(『接続する文芸学』著者)
この本で主に取り上げた3人の作家の作品との出会いは、それぞれ出会いのタイプが異なっている。村上春樹は、初期作品からずっと発表されるたびに読んでいた。最初は、修士課程の頃に後輩が「つるつる読めるよ」と言って貸してくれた『風の歌を聴け』だったと思う。そのつるつる読める作家が、後に世界のムラカミなどと呼ばれるようになるとは、当時思いもしなかった。それから40年近く、村上作品が多彩に展開するとともに私も齢を重ねて、少しずつ書くものにも変化があった。本書に収めた3編の論考は、いずれも人と人との繋がりのあり方に焦点を絞ったもので、最近の読み方を示すものである。ただしこれはむしろ、おそらく40年前の読み方に戻ったというのが近いだろう。
全く逆に小川洋子の作品には、50歳を過ぎてから初めて出会った。『原稿零枚日記』が出た時に書評を書いたことはあったが、本格的に読み始めたのは、学生が研究発表で取り上げ、自分も勉強しなければと思ったのがきっかけである。読んでみると、これがおもしろい。いわゆるポスト村上の小説にあまり興味がなかったが、私の感性にどこかしら響いたようだ。また、小川作品と『アンネの日記』との繋がりにも、大きく心を動かされた。かつて、父の書棚にあった、『アンネの日記』の本邦初訳である皆藤幸藏訳『光ほのかに アンネ・フランクの日記』を読んだ記憶が蘇った。アンネ関係書や、ホロコーストに関する文献が、多数日本語に翻訳されており、それを参照することが容易であったことも、本書の論考を展開するのにきわめて好都合であった。
宮崎駿作品との出会いについては、この二人ともまた異なる。もちろん、国民的なアニメーション作家である宮崎の作品は逐一見ていたが、本格的に論じたのは、大学(前任校)で表象文化論の授業を担当したことが決定的な契機となった。講義において、草創期の『メトロポリス』『フランケンシュタイン』から、ジョージ・パル、ダグラス・トランブルといったアメリカの作家たちを経由して展開した近未来SF映画の系譜において、『風の谷のナウシカ』を考えてみたのである。本書に収めた論考が、イメージ論からみた近未来SF映画論という感触になっているのはそのためである。『風立ちぬ』が封切られるに及び、そこに至るまでの作品系列も、『ナウシカ』と同様の手法で一貫して論じることを試みたのである。
巻末で取り上げた伊藤俊也監督の『風の又三郎 ガラスのマント』は、花巻市の宮沢賢治イーハトーブ館で行われた宮沢賢治イーハトーブ学会のシンポジウムで『風の又三郎』が取り上げられた際、伊藤監督と脚本家の筒井ともみ氏のトークショーとともに行われた上映会で初めて見た。戦前の有名な島耕二監督作品について、かねてより短い論考を書いていたこともあり、いつか論じてみたいと思っていた。武蔵野大学で講演のお話をいただいた際、その思いを実現したのである。七月社から刊行した前著である『〈原作〉の記号学 日本文芸の映画的次元』の延長線上に、「新・〈原作〉の記号学」を念頭に論じたものである。
どれもこれも私にとって、忘れられない大事な作家・作品ばかりである。本書の学術書としての出来映えはともかくとして、これを一著にまとめることができたのは、自分としてはたいへん感慨深い。
*
本書のタイトルは、〈接続する文芸学〉と〈物語は接続する〉の間で最後まで悩んだ。堅めの前者に比べて、後者の方が語感が柔らかく、普及するのに効果的だろうと思われた。ただし、「〇〇は〇〇する」式の題名が最近しばしば類書に見られたことと、いささかなりとも学術書としての性格を示したいと考え、作家名を具体的に副題に入れることで、七月社の西村篤さんとも折り合いがつき、最終的にこのようなタイトルに落ち着いたのである。たぶん、私以外思いつかない、やや奇抜な題名ではないかと考える。
〈接続する文芸学〉という言葉自体は、ここ何年かの間に、講義などで用いてきた。美学・芸術学に基礎を置く文芸学という名称は、純理論的で閉鎖的であり、他に自らを開かないという印象がある。美や芸術性以外の夾雑物・雑音を排除して、純粋な芸術として文芸を認める方法を、岡崎義恵は「文芸学的還元」と呼んだ。「文芸学的還元」には、それなりの論拠と実効性があるだろう。しかし、文芸学の理論史と、それから何よりも私自身の考え方(性向と言うべきか)に照らせば、むしろ文芸のおもしろさや文芸学の可能性は、明らかに一見夾雑物・雑音と思われるような多様性・複数性・例外状態にこそあると言わなければならない。そのためには、純粋・完結した対象として文芸を見るのではなく、自らならざる何ものかと接続されてあるものとしてそれをとらえ、さらにそれを受容することもまた、他者にさらされて自己が変容する様態にあるものとして、理論を整備しなければならないだろう。文芸・芸術・文化の意義は、そのような接続においてこそ見出される。
物語は、それ自体以外の何ものかとの接続において作られ、また受容される。このことは、物語が社会的な現象・行為であることから見て、言うなれば当然のことかも知れない。本書は、ある意味ではそのような物語の基盤に立ち返り、その根元的な見方を少しでも最後まで貫徹しようと試みたものである。
本書がいささかなりとも、そのような意味で、読者との間で接続の回路を開くことができれば幸いである。
変わるもの、そして変わらないもの/西座理恵
変わるもの、そして変わらないもの
西座理恵(『「面」と民間伝承』著者)
本書は「面」と関わる民間伝承(昔話、伝説など)について記しており、博士論文を元に執筆しました。長女の出産後に大学院を満期退学したため、学位を取得するために主婦をしながら大学院に再入学をしました。人生最後の学生生活を送った2020年度はコロナ禍のはじまりでした。その年のお正月に、テレビでコロナウイルスのニュースを目にして、家族とともに「怖いね」と他人事のように話していました。ところがそれは、どこか遠い場所の脅威ではなくなり、世界中の日常生活を送る人々に影響を及ぼし始めました。新年度の学校は中々再開されず、初経験のリモート授業となり、大学の図書館に出向くことも難しくなりました。
2020年前半のコロナ禍で多くの家庭の主婦が直面した問題の一つに、毎日の食料の買い出しと食事作りがありました。古今を問わず、主婦は様々な家事を担ってきたようです。本書のⅠ部では「肉附き面」という昔話を取り上げています。この昔話では、姑が説教を聞くために寺参りへ行く嫁を、道の途中で鬼面を付けて待ち伏せし、脅します。すると、鬼面が姑の顔から外れなくなります。また姑は嫁から寺参りの時間を奪うために、多くの仕事を言い付けます。その仕事の内容は米や雑穀を臼で挽く、繊維を紡いで糸にするというものでした。以前、群馬県の六合村を訪ねて年輩の女性からお話をうかがったときに、戦後の物のない時代には手ぬぐい一つも自分で作ったと聞きました。現在ならば、買いに行くとすぐに手に入る一本のタオルを自分で作るという話に、その大変さが思いやられました。また、本書で取り上げた『官刻孝義録』という書物のなかには、農業、小さな商い、介護に奮闘しながらも両親、義父母そして夫に従順に仕える女性の姿がありました。洗濯機、冷蔵庫、掃除機、どれか一つが壊れても家事がままならないと嘆き、ストーブの灯油がなくなり、パソコンで間違ったボタンを押す度に慌てて夫に告げる私には、とても昔の嫁は務まりません。
また、コロナ禍で世の母親たちが直面した問題の一つに、子どもたちの学校の休校があったと思います。子どもが学校に行っている時間が博士論文の執筆時間になるため、私にとって小学校の休校は緊急事態でした。そのような中、子どもを公園にも行かせづらく、我が家も映像配信サービスに子守りを頼り、当時小3の娘はアニメ『鬼滅の刃』に夢中になっていました。話の内容を知らなかった私は、人が殺されたり、血が飛び散ったりする場面を目にして、子どもに見せてもよいのかと不安を抱くと同時に、それまで怖い話を嫌った娘が夢中になっていることが不思議でした。ですが、物語のあらすじや主人公の優しさを興奮気味に語る子どもの様子と自身の時間のなさに、見るのを止めさせることはできませんでした。結局、子どもが夜中に怖い場面を思い出して起きたり、泣いたりしなければ、アニメを見せることにしました。後に私も『鬼滅の刃』の漫画本やアニメから、貧困や弱い立場にある人々が迫害を受けて鬼になる様子や、鬼を倒す少年が鬼になった人の生い立ちを憐れむ気持ちも描かれていることを知りました。
本書では吉田綱富『童子百物かたり』第五十話「酒呑童子のこと」という話を取り上げています。この作品でも「酒呑童子」が「童子だって、生まれたときからの鬼ではない。父もあれば、母もある」と語ります。そして、酒呑童子を倒しに行った武者たちは酒呑童子の話に耳を傾けて涙を流します。また語りの場面では、八歳の男の子が按摩坊の「酒呑童子」の語りに耳を傾けて楽しみます。ここには、勧善懲悪な「酒呑童子」の物語とは少し違った話の要素がみられます。鬼を「悪」の側面からのみ捉えない点や子どもたちが鬼退治の話を楽しむ様子から、時代や媒体は違えども人が心をひかれる話には何か共通するものがあるのかもしれません。「酒呑童子」が鬼になるまでを描く話は多くないのですが、本書のなかでは伝説やお伽草子といったジャンルの話を取り上げており、お伽草子『伊吹山酒典童子』では、顔から「面」が離れなくなった稚児が「酒典童子」になります。
博士論文の執筆のために様々な資料にあたるなかで、古典の時代を生きた人々がもし現代の生活を知ったなら、どのように感じるだろうかと考えることがありました。現代の私たちは、遠い場所に住む人とモニターを通してではありますが、顔を見て話すことができ、家事の多くを家電に任せることができます。しかし、家電が発達しても嫁姑問題が消滅したかと言えば、いまだ人間関係における葛藤の一つとして存在します。そして相変わらず、鬼や妖怪を退治する話は子どもたちに大人気です。また、現在のコロナ禍でも昔の人々が行ったように疫病退散を祈る行事が全国各地で行われています。このように考えると、人の心は古今を通じて容易に変わるものではないように感じます。心の周辺を描く様々な文化的作品が人々を魅了し続ける要因はそこにあるのかもしれません。本書は研究書ではありますが、民間伝承を通じて昔の人々も現代の人々と同じように人間関係に悩んだり、鬼の話を楽しんだりしながら日々を生きていたというようなことも感じて頂ければ、筆者としてうれしく思います。
「ヨソ者」の利点/桐村英一郎
「ヨソ者」の利点
桐村英一郎(『木地屋と鍛冶屋』著者)
新聞社を定年退職後、生まれ育った東京を離れ、奈良県明日香村で六年ほど暮らしたのち、三重県熊野市波田須町に移り住みました。大都会に出るのに時間がかかるけれど、それがまた居心地よく、借家の窓から熊野灘を眺める生活もいつの間にやら十二年目です。
コロナで海外旅行もままなりませんが、ある住民が「ここには海も山もいっぱいある。わざわざ外国まで出かけることはないよ」と言うのを聞くと、それもそうだと思います。まあマスクをせずに散歩でき、ときおり鹿や猿に出くわす日々は悪くありません。
明日香村の時代、そして熊野に来た時分の興味の対象は古代史でした。現役時代は経済記者でしたから、歴史はずぶの素人。でも「シロウトのヨソ者」にもメリットはあります。それは「見るもの聞くもの新鮮で、しがらみがない」ということです。
熊野の第一作は『熊野鬼伝説』という題で、坂上田村麻呂の鬼退治伝説の背景をさぐってみました。明日香村で住んでいた地区は、田村麻呂の父・苅田麻呂ともつながる渡来人が古代に定着したところです。ですから私には京の都にいた田村麻呂の知識も多少ありました。八世紀末から九世紀初頭の蝦夷征討で有名な田村麻呂は鈴鹿峠を何度も行き来したでしょうが、熊野には来ていないはず。それなのに近辺の鬼ケ城、泊観音、大馬神社などに彼の鬼退治伝説が根付いているのはなぜだろう。そんな素朴な疑問が探究に駆り立てたのです。
そこにはどうやら『熊野山略記』というネタ本があったようです。この中世文書には「熊野三党(地元の豪族)が南蛮(南から来た海の民)を退治した」とあります。これら化外の民が鬼になり、天皇の命で制圧した熊野三党が田村麻呂になった。そう推測しました。
熊野は昔から漁民、修験者、そして三山への参拝者など東北地方との交流が少なくありませんでした。近世になって伊勢路沿いの社寺が英雄譚を自社の縁起に取り入れた。そんな事情もあったと思います。地元の人は子供のころから聞かされ当たり前に思う伝説や伝承を新鮮な目で見直し、自分なりの仮説を立ててその立証を試みるのは楽しいものです。
次の作品『イザナミの王国 熊野』の仮説はもっと突拍子のないものでした。熊野三山のカミ、すなわち熊野速玉大社の主祭神・速玉(早玉)神と熊野那智大社の主祭神・夫須美(結)神の原郷はインドネシアのセラム島だ、なんて説を唱えたのです。
詳しくは拙著をお読みいただくしかありませんが、ハイヌウェレという南島の穀物創世神話が黒潮に乗って熊野に流れ着き、「結早玉(むすびはやたま)」という熊野独自の神格に育った、と考えました。
明日香村時代、古代史の泰斗である故上田正昭先生にお世話になりました。『大和の鎮魂歌』に一文を寄せていただき、次の『ヤマト王権幻視行』では「幻を見たんじゃ批判できないなあ」と私をからかいながら、歴史地理学の千田稔氏と一緒に巻末に載せた座談会に参加してくださいました。
「君は気楽になんでも書けていいなあ」「つまらない古代史マニアになりなさんなよ」といった先生の言葉を思い出します。仮説検証型のアプローチをする場合、できるだけ文書や書物に当たる一方、現場を訪ねて自分の目で確かめる。そして専門家が「もしかしたら、そんな可能性もあるかもしれない」と思うぐらいまで迫ってみたい。そう自分に言い聞かせてきたのは、上田先生のそんな言葉がいつも頭にあったからです。
私はこれまでもっぱら古代史の探究を楽しんできました。それが七月社から出版した『木地屋幻想』で一気に近世に飛んだのです。木地屋(木地師)は山中に暮らし、トチ・ブナ・ケヤキ・ミズナといった木を刳り抜いて椀や盆などを作る職人です。なぜ彼らに惹かれたか、は『木地屋幻想』やその続編でもある今回の『木地屋と鍛冶屋』のあとがきをお読みください。古代に黒潮に乗ってやってきた人々にも、山々を渡り歩いた漂泊民にも、火と水と風を操る鍛冶屋にもロマンを感じます。
『木地屋と鍛冶屋』には現存の方々とその家族が登場します。時代は下っても「仮説を立てて、その検証を試みる」という手法は変えていません。それは「家系の謎解き」のくだりです。拙著を開いてご覧になってください。