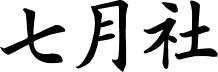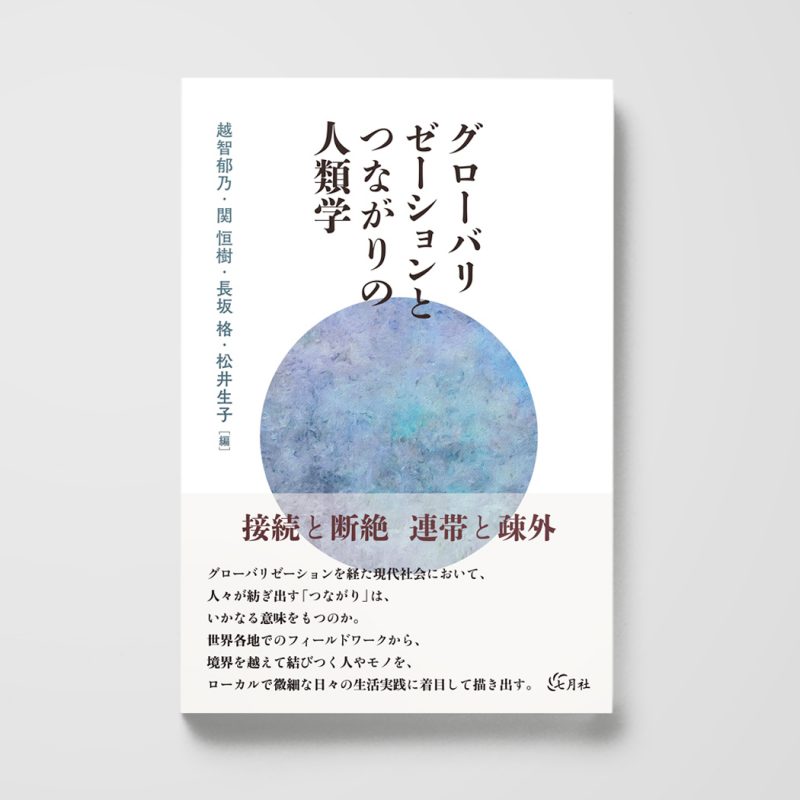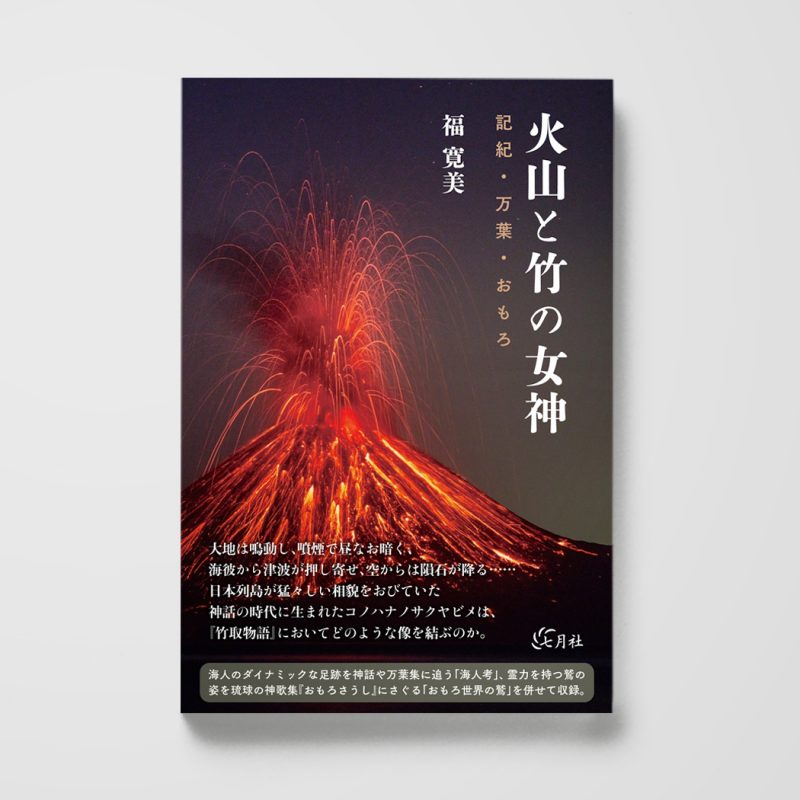昭和11年、安家の夏
岡惠介(『[増補改訂版]山棲みの生き方』著者)
私は昭和61年、筑波大学環境科学研究科の研究生をやめて北上山地の奥地山村・安家(あっか)に移り住み、岩泉町の教育委員会の仕事をしながらフィールドワークを進めていった。
なぜ調査フィールドを安家にしたのかとよく聞かれるが、その理由は一言では説明しにくい。しかし確実に一因をなしているのは、山口弥一郎氏の著作である。山口弥一郎氏は明治35年に会津に生まれ、昭和15年から21年にかけては岩手県内の中学、高校などでも教鞭をとった経歴を持ち、東北各地を歩いて地理学や民俗学分野のフィールドワークを行った。なかでも昭和8年の昭和三陸地震による津波被災地の暮らしや復興過程の研究は、東日本大震災後に大きく評価され、昭和18年刊行の著書『津浪と村』が復刊されている。
山口の仕事は山村にも及んでおり、焼畑もテーマのひとつだった。『東北の焼畑慣行』(恒春閣書房、昭和19年)に収められた「北上山地の山村と焼畑」の冒頭に置かれた「一、採訪記」という85年前に書かれた痺れるような一文がある。これを読むたびに、私は安家の昭和11年の夏に連れ去られ、炉端で村人たちの歓談を聞いているような気にさせられる。
採訪記の中で最初に訪れる民家は誰の家であり、屋根はトタンに替えたがあとは当時の囲炉裏もそのままであると判明したり、知り合いになる村会議員は誰で、年老いたその彼と一緒に酒を飲んでからまれ酷い目にあったといった体験が、私の幻視のリアリティを増加させるのかもしれない。中略をはさみながら引用してみよう。
一、採訪記
日本人の古い生活様式が、下閉伊の安家程の僻村になれば、相当は窺ひ知られようと、昭和十一年八月、当時福島県にゐたので、遥か北へ旅する心地ででかけて来た事がある。
盛岡より山田線に乗換へて、茂市へ下車すると、当時一日に二回かの岩泉行バスがあった。これも現在は小本線が岩手和井内駅まで開通して、そこより岩泉行のバスが立つやうに改められてゐる。岩泉まで行けば何んとかなるだらうと、下り立ってはみたが、雨は降って来るし、乗合自動車は通っていない。
私がはじめて安家に入ったときは、茂市から岩泉線(山口のいう小本線)が岩泉駅まで到達していた。しかし現在では岩泉線は廃線となっている。山口が岩泉線を小本線というのは、当時岩泉から太平洋岸の小本までさらに延伸する計画があったからだが、これは実現することはなかった。
こんな時は、よくも苦労して物好きに来たものであると言ふ感じが一寸頭をかすめる事もある。然しすぐ東北研究に献げた自分の念願に落着き、雨の中を六里余の山道を歩く決心をし、邪念を払って、軽い気分でポツリポツリと歩き出す。宇霊羅山を廻って北の谷を登ってゆくのだが、道路は改修されて広いし、雨に洗はれて堅い。
こうして全身汗と雨に濡れながら安家に入り、一軒しかない「宿舎と言ふには名ばかりの一民家」にたどり着くのだが、そこからのこの民家での村人とのやり取りは、まさにわたしたちを85年前の山村に連れていってくれる。
入口の薄暗い破れ障子の間には、雨に閉ぢ込められたらしい、傘直しの老人がポツンと諸道具を前にして、煙草をのんでゐる。先づ今晩の宿を頼んで上がらうと、左の炉のある方へ廻ってみた。ここには四、五人の請負人と村人らしいのが酒を交して談笑してゐる。私がはいって行くと、先づ視線が私の頭から爪先までなでおろされたのを感じた。そして開口一番村人の言葉は「何商売ですか」である。随分と永い間東北の山の旅を続け、種々の職業者に見間違ひられることになれてゐる筈であるが、これは又余り突飛に、私の感じ方と異なってゐたので、意外な面持にならざるを得なかった。然し直ぐ、旅なれた気持を取り戻して、「さあ特別商売と言ふ理ではないが」と、御免してもらって、炉辺の一隅にかけたものである。
「商売と言ふ理ではないが」と言った最初の言葉は、行商人である事を肯定した意味にもとれたかどうかして、私の行商の種類を詮索しようとかゝる。漸次売る物をもたぬとみると、何か請負人か山師とでもみたか、今度は商売敵の如き口吻がもれて来る。村の伝説や昔話を聞き度い等と言ってみても、此の世の中に、この僻村に雨の中を旅して来る物好き等は、到底考へられさうでもなく、漸次兜をぬいで、名子の事を聞いてみたい為はいって来たと話した。
さうすると中年の一村人が、「名子の事なら詳しく知ってゐる。俺は村会議員である」と向き直って言ったものである。
これは漸次わかって来た事であるが、酒を交してゐた人々は、他村よりはいって来た炭旦那即ち山を買って、焼子を雇ひ、製炭を請け負う山師と、山を売らうとする村人や、焼子の一群で、相談のまとまった、祝ひ酒の場所であったのである
一旦気持がほごれると村会議員と言ふ人の居丈高な気分は失せて「名子の事ならここでは話せない。この家も玉沢さんと関係があるから。家には老人もゐて話がわかる」と、滞在中は一度寄って呉れ等親しく話して呉れる。それなら今日にも行ってもよいがと言へば、雨の中に、山道で容易でないと言ふ。いやそんな事は一向苦にしてゐない。身体の傷む事は既に覚悟は出来てゐて、心軽く旅して来てゐる。と話して行けば、私の熱心にほだされてか、既に夏の日も夕暮近い山道を、約一里半程も安家川に沿うて下ったのであった。
安家の場合の名子とは、ダンナサマと称される酒屋や商家を兼ねた山林大地主への借金のかたに、家屋敷や耕地、山林、採草地、家畜などの所有権を奪われ、それらを貸与されて生活し、ダンナサマの畑や家畜の小作を行い、年間定められた日数を農作業などの賦役に服し、冠婚葬祭の手伝いも義務付けられた主従関係にあった人々のことである。一般に地頭名子制度と呼ばれ、戦前の社会経済史では注目度の高いテーマであり、岩手県北地域には多く見られたが、村人の口は重く調査は困難を極めた。安家での最大のダンナサマは玉沢家であったが、その起源は意外に新しく、明治以降のものだと言われている。戦後の農地解放で名子は消滅したが、筆者が安家での調査を始めた頃も、ダンナサマの牛を飼って生まれた子牛の販売代金を折半する牛小作は残存していた。
山口はこの後、安家の年々(ねんねん)という集落に着き、名子についても聞いたであろうが、まだこの集落のワヤマで行われていた焼畑について、詳細なヒアリングを行ったはずである。
あの一筋縄ではいかない、一見猜疑心の強そうな、しかし打ち解ければ底抜けに人のいい安家の人々とまた会って話がしたい、そう思わせる名文である。ふつうは論文に組み込まないであろう、このような採訪記をどうしても冒頭に置きたかった山口の気持ちが慮られる。こんな出会いをしたいという願いが、安家で調査を進める原動力のひとつだった。
調査を続けていった末に、私は安家に家を建てて家族と棲むようになった。その頃私はフィールドワーカーという立場を超えたと思っていた。しかしその後勤務していた久慈の短大の閉校でやむを得ず安家を離れ、約20年が経とうとしている。一度はフィールドワーカーから安家の人になった自分が、今はまたアウトサイダーとして安家の本を書いている、その自分の引き裂かれた立ち位置も、山口の名文に惹かれる理由であるのかもしれない。