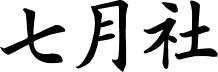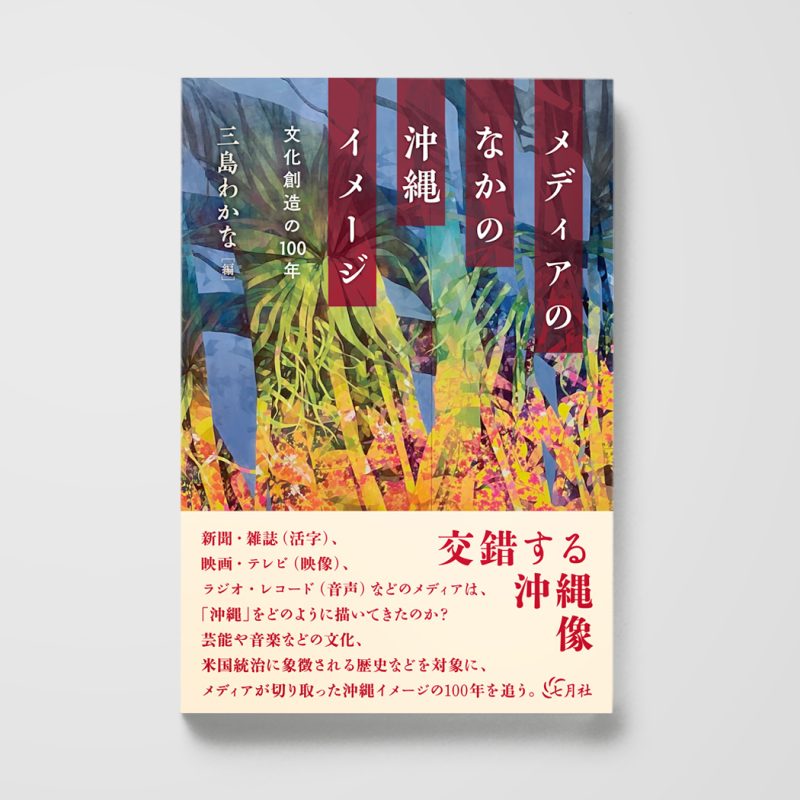《悲しきマングース》に込められた沖縄の近代とその後
三島わかな(『メディアのなかの沖縄イメージ』編者)
畑のなかにうずくまる マングースの悲しみは 空の月さえわからない ♪
この歌詞は、《悲しきマングース》(作詞:前史郎、作曲:中村和)の歌い出しの一節。本書の第1章でも登場するNHKのテレビ番組「みんなのうた」のオリジナルソングとして1979年12月~1980年1月に放送され、ハブ被害に悩まされた近代沖縄社会へマングースが導入された史実にもとづく歌である。放送当時、9歳で小学校3年生だった筆者の記憶にも、ちょっぴりセンチメンタルな曲調とアニメーションで独特な動きをするマングースのもの悲しい表情も相まって、この歌は鮮烈さをもって刻み込まれる。そして、この歌は次のようにつづく。
インドはデカン高原を 遠く離れて来たけれど ここは沖縄ハブの島 ♪
マングースと沖縄との関係は、今から115年前の明治期末へとさかのぼる。当時の新聞記事にも「マンちゃん沖縄にやってくる」とうたわれており、新たにこの地に導入されたマングースによって、当時、サトウキビ農園に大きな被害をもたらしていたハブやネズミが駆除されるであろうことを、沖縄の人びとが期待していたことがわかる。在来種のハブやネズミを駆逐する目的のもと、外来種のマングースが沖縄にもたらされたのだった。
ここで、歌の内容に話を戻そう。《悲しきマングース》の歌詞のなかでは、「インドはデカン高原を……」と歌われるが、実際のところ、動物学者の渡瀬庄三郎(1862~1929年)が沖縄本島南部へ連れてきたマングースはデカン高原からではなく、ガンジス川河口(現在のバングラディシュ)に生息していたフイリマングースだった。本書の第1章においては、「沖縄の史実」や「沖縄イメージ」が投影される一曲として《悲しきマングース》を紹介したが、この歌には同時に日本人が想起するところの、きわめて漠然とした「インド・イメージ」も浮かびあがる。すなわち前出の歌詞にみられるように、インド北東部を流域とするガンジス川もインド南部に位置するデカン高原も、はたまたバングラディシュもインドも、これらの間に介在する地理的な隔たりや文化圏の違いに頓着することなしに、この歌のなかではこれらを「インド」の名のもとに一絡げにしてしまっているのだ。インドやバングラディシュのことを「知らないが故」の誤解を生じている。一方的なイメージの構築には、一種の暴力性や危険性をともなう。そして、この歌はさらに次のようにつづく。
皮を剥がれてこの姿 マングースの悲しみを 明日はどなたが消すのやら ♪
月日は変わり身は変わり マングースは疲れ果て 空にゃポッカリ白い雲 ♪
背中を丸め逃げた日も 涙隠したこともある それはハブにもわかるだろう ♪
人間の立場からすると、マングースが退治すべき敵であるはずのハブに対して、なぜかマングースは思いを寄せ、その歌詞にはマングースとハブがあたかも同志のように描かれる。暗喩ではあるが、人間こそ、マングースとハブにとっての敵なのだ。そして、この歌は次のように締めくくられる。
夢は破れてこの姿 マングースの優しさを どこのどなたが知るのやら ♪
雨降る夜はなお悲し マングースは穴の中 遠いふるさと思い出す ♪
製糖業は沖縄県の基幹産業であり、農業や産業の振興のためにもサトウキビ農園をハブやネズミの被害から守ることは人間界の論理からすれば当然だった。だからこそ大義名分のもと、マングースはハブ退治のために沖縄へと導入された。けれども、立場を変えて自然界の論理で考えるならば、人間の身勝手な行為によって、マングースは生まれ育った環境のもとに生きることを断たれたのだ。その悲痛な思いが、メッセージとしてこの歌に込められる。
このように近代沖縄では人間の犠牲となったマングースだが、それにもかかわらず、マングース導入という渡瀬の策は功を奏さなかった。その後もハブは根絶することなく、現在もなお沖縄本島にはハブもマングースも生息する。なぜなら、昼行性のマングースがわざわざ夜行性のハブを捕食しなくとも、他にも昼行性の生き物がいっぱいいるためだった。
そののち、20世紀後半にもなるとマングースの生息域は当初導入された沖縄本島の南部から北上し、「ヤンバル」と呼ばれる沖縄本島北部にまで広がった。そして、1981年に本島北部の国頭村で発見され天然記念物として指定されているヤンバルクイナはマングースや野猫によって捕食され、その生息数が激減したという。本来、マングースはハブを退治するために人為的に導入されたが、その策も失敗に終わり、それどころか在来生物を捕食し生態系のバランス崩壊へ……、どのように対策するかが現状の課題となっている。
本稿では、本書の第1章「原風景から多元的な自画像へ──テレビ番組「みんなのうた」が描く現代沖縄像」に登場する歌のひとつ《悲しきマングース》に着目して、この歌の世界から立ちのぼる近代沖縄社会と「インド・イメージ」に潜む暴力性、さらには、こぼれ話として沖縄社会の現状と課題について紹介した。そして、本書の第2章~第7章ではそれぞれに、雑誌や新聞、映画、ラジオやレコードといった各種メディアを介して、「沖縄」のこの100年がどのようにイメージされてきたのかに鋭く迫っている。
文化創造とイメージの多様なありかたは、現在のわたしたちの価値観とどのようにつながっているのだろうか……。ぜひ、本書を手に取ってお読みいただきたい。