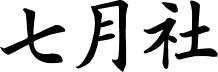〈出会い〉の記号学
中村三春(『〈原作〉の記号学』著者)
かつて仙台で大学の助手をしていた頃、街にヨーロッパ映画を多く上映する映画館ができて、足繁く通っていた。とはいえ、その後地方大学を転々とする身で、本職の文学の方が忙しく、どこで映画と文芸との関わりにめぐりあったのか。想い起こすと、トニー・オウ監督の『南京の基督』(1995)に行き当たる。芥川龍之介原作だから、文芸映画と言ってよいわけだが、なぜこれを見たのかよく覚えていない。しかも、文芸原作の映画化であるが、私が着目したのは、映画がたぶんあまり意識もせずに原作から変更した作中人物の髪の毛の色に過ぎない。しかしそこを切り口に読み直し、見直すと、原作の「南京の基督」の持つ意味がこれまでとは大きく違ったものに思われてきた。髪の毛の色の変更という些末な事柄も、やはり文芸テクストの解釈にほかならず、また細部の解釈は必ずや全体の把握にも波及するのだ。この作品や、この作品にまつわる原作現象との出会いが、文芸における映画的次元の追究へと向かう契機となったことは間違いがない。いつどこに出会いがあるのか、本当に分からないものである。
この十年来、科研費の研究課題であったため、1950年代の日本映画を重点的に見て問題を探っていたが、そんなある時、岩波書店『文学』の「文芸映画の光芒」特集に執筆の依頼を受けた。編集部と相談しながら、篠田正浩監督の『心中天網島』(1969)を論じることにしたのだが、原作の近松も浄瑠璃も篠田監督作品についても、いずれも全くの勉強の仕直しであった。にもかかわらずこのテーマに決めたのは、同じ近松作品を下敷きとして、義太夫節を愛した太宰治が晩年に「おさん」(1947)という小説を書いており、かつてそれを論じていたからである。篠田監督の『心中天網島』は古典に題材を採った超絶的な前衛作品であるが、太宰の「おさん」も太宰的な絶唱の一つである。ただし、「おさん」は同時期の『斜陽』や『ヴィヨンの妻』に比べると評価が高くなく、私はこれを取り上げたことに思い入れがあった。原作現象は複数のジャンルをまたぎ、複数の作者の創作を包んで拡がる要素がある。それにしても依頼を受けなければ、本気であの超絶的な『心中天網島』に立ち向かうことができただろうか。このことも一種の出会いというか、意想外に到来する契機であったのだろう。
しかし出会いと言えば、まさに科研費の共同研究のメンバーたちとの出会いをも忘れることはできない。私は研究代表者を務めたが、研究水準においても代表であったとは到底言えない。多士済々で個性的な多くのメンバーたちに教えられ、鼓舞されて共同研究を進めたのである。その中でも国際派の日本文学・文化研究者である中川成美氏が、パリの日本文化会館で川端康成展が開催されるのに併せて、科研費によるワークショップをパリで行うことを提案された。当初の予定になく、国内での活動に限定していたので驚天動地だったが、何とか準備を整えて2014年10月に川端原作の文芸映画に関するワークショップの実現に漕ぎつけ、私も豊田四郎監督『雪国』(1957)に関する研究発表を行った。そこでフランスの研究者との新たな出会いがあり、また研究に関する視野の広がりを得た。その成果は中村三春編『映画と文学 交響する想像力』(2016、森話社)に収録されている。出会いというのは、予想できないものであり、予想できない結果を生むものである。
原作現象の研究は、いずれにせよテクストと第二次テクストとを接続する操作に関わるのだが、考えてみれば私たちの生命も文化も社会も、自己と他者との意想外の出会い、あるいは接続の連なりにほかならない。出会いという現象は、接続という機能の一般理論的な追究に結びつくものではないだろうか。私は目下、文芸を中心として、様々な生命・文化・社会にも通じるような、接続の理論を構想しているところである。