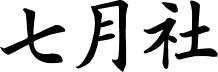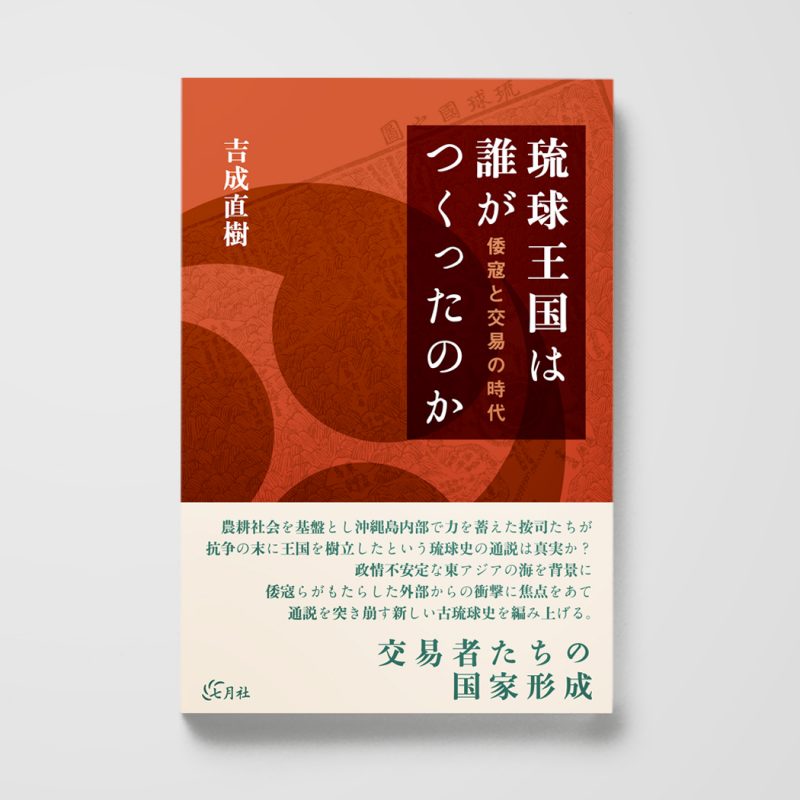歴史という「物語」
吉成直樹(『琉球王国は誰がつくったのか──倭寇と交易の時代』著者)
新たに刊行した『琉球王国は誰がつくったのか──倭寇と交易の時代』は、従来の古琉球史研究に対する批判であるとともに、その批判を踏まえて自分なりに古琉球史像を描くとすれば、どのようになるのかという試みである。
古琉球史研究に対する批判とは、古琉球時代の琉球国を過大に評価することによって生じる研究のゆがみ、またそれによって史資料の扱い方にさえ制約を与えてしまうことに対する批判である。言うまでもなく、「古琉球時代の琉球国が栄華を誇ったことはない」などと主張しているのではないことをあらかじめ強調しておきたい。
ひとつだけ例をあげて、本書の紹介としたい。
琉球の三山を統一することになる思紹(ししょう)、尚巴志(しょうはし)が佐敷按司の時代に拠城としていた佐敷上グスクをめぐる問題である。なお、尚巴志が思紹の後を継いで佐敷按司になったのは1392年、21歳の時であったとされる(『中山世譜』)。
琉球文化圏には、城壁で囲まれた大規模な城塞型の大型グスクと、尾根や台地の先端部地域を、堀を入れて本体と切り離して安全を保つ全国の中世城郭にみられる築城法を用いた「グスク」が存在する。佐敷上グスクは後者に位置づけられ、高石垣を伴わず、主に切岸と空堀で造った曲輪を主郭とする、全国の中世城郭様式による山城であるとされる(三木靖『鹿児島県奄美市 史跡赤木名城跡保存管理計画書』奄美市教育委員会、2015年)。
佐敷上グスクは琉球的な城壁を伴うグスクは異なり、本土的な構造を持つ中世城郭であり、系譜の異なる構造物ということになる。こうした佐敷上グスクに類似する構造を持つ中世城郭跡は、奄美大島の赤木名グスク、喜界島の七城のほか、沖縄島北部地域の根謝銘グスク(大宜味村。謝名グスクとも呼ぶ)、名護グスク、親川グスク(名護市)をその代表にあげることができる。このほかにも国頭地方にいくつかの事例がある。
佐敷上グスクは、14世紀後半を中心に16世紀までの年代が与えられているが、14世紀後半以降は沖縄島の各地で造営される琉球的な大型グスクの構造化(基壇建物の建造や大規模城壁の造営など)が進む時期であり、それと同時期に盛んに利用されていたことになる。壮大な城塞型の大型グスクが形成されていく時期に、中世城郭の構造を持つ佐敷上グスクを思紹、尚巴志は拠城としたのである。
こうした中世城郭は、もちろん本土地域から渡来した技術者によって築城されたと考えられ、そこを拠点とする人びとも本土地域から渡来した人びとと考えられる。築城した技術者のみが本土地域の人びとであり、そこに拠っていた人びとは沖縄島社会の人びとであったとは考え難い。中世城郭跡の分布を考えても、琉球国の統一を成し遂げた思紹、尚巴志の出自はもともと本土地域であったと考えられる。
従来の研究では佐敷上グスクのような中世城郭の様式を持つグスクには「土より成るグスク」などの名称が与えられ、琉球的なグスクの前代のものとされ、時間的前後に置き換えられたり、琉球型のグスクのカテゴリーの中に位置づける──この場合は立地の地形や地質などの違いが強調される──ことによって理解されてきた。
なぜ、そのような理解の仕方になるのかを考えると、沖縄島社会の発展は「琉球王国」へと向かう単線的な発展を遂げたとする見方があったと言わざるを得ない。それは、多様な史資料を「琉球王国」にいたる過程に直線的に並べる思考にほかならない。その背景には「琉球王国」を絶対的なものとみなし、すべてはそこにたどり着くという歴史観があったことによる。こうした見方による弊害は、高梨修氏(奄美市立奄美博物館)、池田榮史氏(琉球大学)によって、つとに指摘されてきたことであった。
こうした歴史観に立つと、内的発展論への過度の傾斜、主体性・自立性の強調もまた、歴史描写の際の特徴として現れることになる。こうした特徴は、外部からの影響、ことに外部からの人びとの移住による影響をきわめて低く見積もることにつながる。
このたびの本は、こうした制約から離れるとどのような歴史像を描くことができるか、またそのような歴史観がどのようにして形成されたのかを明らかにしようとした試みである。後者については、前著『琉球王権と太陽の王』を刊行したときに、本欄「ほんのうらがわ」に掲載していただいた「沖縄研究と観光戦略」を発展させたものであり、1975年の沖縄海洋博の沖縄館の展示構想までさかのぼって跡付けたものである。このテーマは、歴史という「物語」が人びとによって、どのように受容され強固に共有されるようになったのかを明らかしようとする試みである言い換えることができる。「物語」とはフィクションを意味するものではないことは言うまでもない。