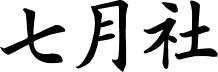鷗外、〈心〉をめぐる詩学
新井正人(『鷗外文学の生成と変容』著者)
日本でもっとも有名な近代小説は何か。
こう問われれば、おそらく多くの人が夏目漱石「こゝろ」(1914.4.20-8.11)を挙げることだろう。新潮文庫版の累計発行部数は1位。高等学校の教科書にも採録され続けている。たしかに、「こゝろ」は人々に読み継がれているようだ。
今から百年あまり前、「こゝろ」の単行本化(1914.9)に際し、漱石は「自己の心を捕へんと欲する人々に、人間の心を捕へ得たる此作物を奨む」と新聞広告に書いた。広告文は同時代の読者に訴求するものでなければならない。そうであるなら、なぜ、こうした文言が広告文たり得たのか。
坪内逍遙は、日本近代文学の成立を画す評論『小説神髄』(1885.9-1886.4)において、数ある文学ジャンルの中から、とりわけ小説を自律的な芸術作品として特権化した。その際小説は、当時最新の学知であった心理学の知見を援用して、人間の内面心理を描き出すものであるべきだとされた。近代文学は、「人間の心」に特別な関心を寄せ、それを言葉によって「捕へ」ようとする小説表現として生を享けたのである。
その後明治期を通じ、「心」を中核として人間存在を捉え、それを描き出すものこそが小説であるとする意識は、徐々に人々のあいだに浸透した。なぜ、「こゝろ」の広告文があのような形で書かれたのか。もはや明らかだろう。それは広告文が、「こゝろ」を当時の小説規範を体現する作品として位置づけ、読者に提示するものだったからである。
そして、こうした規範は、近現代における文学のありかたを大きく規定する力をもった。多くの文学が「人間の心」を精細に語ることで小説たり得た。教育の場では、そうした小説が教科書に採録され、試験においても出題され続けた。私たちは、時に主人公の苦悩に共感し、時に心情の変移を主人公の成長として読む。さらには、読解を通じて自らの内面を凝視し、省みることを求められる。心情中心主義は私たちの読解を律し、自己認識のありかたにも影響を及ぼしている。
だからこそ、「人間の心を捕へ得た」「こゝろ」は、「自己の心を捕へんと欲する人々」によって近代文学の代表作とみなされてきたのである。
ところで、「こゝろ」を筆頭に、漱石文学は現代にも多くの読者をもつが、森鷗外の場合はどうだろうか。「舞姫」(1890.1)や「高瀬舟」(1916.1)など、一部の作品が教科書に載り続けてはいるが、漱石と比べて、取っつきにくい、わかりにくいと感じる人々が多いのではないか。
他でもない、かつての私自身がそうだった。とりわけ、晩年の歴史小説や史伝については、どのように受け止めたらよいのか戸惑うばかりだった。なぜ、鷗外文学はこうした違和の感覚を懐かせるのだろう。今から考えれば、そうした素朴な問いが本書に結びつく研究の端緒にあったように思う。そしてそれは、私自身が文学や小説に対してもってしまっていた先入見を、少しずつ解きほぐしていく作業でもあった。
世界史的に、近代文学と近代心理学の成立は、あたかもコインの表と裏の如く現象した。両者の共犯関係のもとに、人間存在は内面的主体として見出され、言葉によって表現されることで明確な姿形を与えられていった。事態は日本でも同様である。明治期、欧米の近代心理学が移入され、俗化しながら一般に浸透する過程と並行して、日本近代文学はその形を整えていった。まさに逍遙が意図したように。
こうした観点からみれば、鷗外文学はすぐれて同時代的な表現実践であったと言える。当時西欧では、心理学を諸学の基礎に据え、世界の事象を心理的な内容や過程に還元して理解しようとする心理主義が席捲していた。鷗外は、こうした〈心〉をめぐる諸学知を引き受け、極めて学理的に自らの文学を構築した。鷗外文学は、いわば〈心〉をめぐる詩学なのである。
だが、その営みはすぐれて近代文学的でありながら、同時に、当初からそれとは異質な何かをも抱え込んでいた。潜在し、ときに顔を覗かせたその水脈は、晩年の文業に至って流露する。鷗外文学を読むことは、心理学的な近代文学の範疇に収まらない、文学の別様へと読者を誘う。
本書は、鷗外の文学的営為の分析を通じて、心理学を中心に編制された世紀転換期西欧の〈心〉をめぐる諸学知が、近代日本において如何に受容され、展開されて行ったのかを実証する試みである。それは「人間の心」に中心化された近代文学を築きつつも、そこから超え出てしまった言葉の集積として鷗外文学の動態を捉える試みでもある。
そして、近代文学を相対視することは、私たちが生きうる生の多様性に改めて目を向けることへと繋がるだろう。近代文学をめぐる制度が産出した内省する主体は、ともすれば内面という隘路にはまり込む。その息苦しさからの出口は、おそらく、意識された内面の外部、自己の外側へと目を転じ、それを受け容れたときに見えてくる。
鷗外文学は近代を内在的に批評する。その言葉の集積は、近代の臨界点を生きる私たちに対して、別様の人間像や世界観への想像力を喚起するものであり得るだろう。
* * *
本書の刊行が、このような社会情勢の下でなされることになろうとは想像できなかった。
新型コロナウイルス感染症の世界的流行は日本にも及び、感染爆発は回避したとされるものの、いまだ終息は見通せない状況にある。感染症は徐々に私たちの日常を侵蝕した。そして、「緊急事態宣言」下において、公衆衛生的な知と権力の遍在は明らかなものとなった。私たちは、生き延びるため、社会を守るため、日々絶えざる「自粛」を求められた。その後に到来するのは「新しい日常(ニューノーマル)」であるという。
知られるように、鷗外は日本で最初期の公衆衛生学者の一人だった。日本人による衛生学教科書の嚆矢『衛生新篇』(1897.6)の刊行など、様々な媒体を用いた啓蒙的言説の産出に加え、陸軍軍医総監・陸軍省医務局長就任後には、軍内における腸チフスの予防接種を主導した。
こうして見ると、鷗外は公衆衛生的な知による個々人の統括を目論んでいたように見える。実際のところ、そうであったに違いない。だが同時に、事態はそう単純なのかとも思われる。鷗外はその文学的営為を通じて、近代的な主体、現下の私たちがそうであることを求められ、また自らそうあろうとした自律的主体が、否応なしに有してしまうしなやかさを仄めかしていたのではないか。生きさせる権力の網の中にあっても自らを変容させ、社会をも変容させ得る生の可能性。
私は鷗外の遺した言葉から、私たち自身のそうしたありかたへの勇気を汲み出したい、と思う。